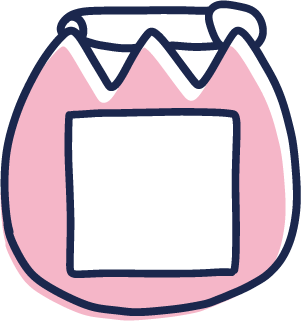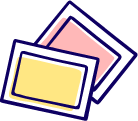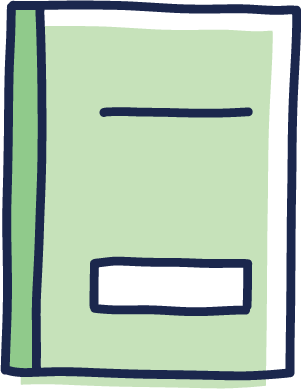
園長便り2025-03
2025.05.09
「不思議を観察する」
園長:中村貫太郎
桜が満開の時期を過ぎ、幼稚園の園庭もようやく春らしくなってきました。サクランボの木やムスカリも花を咲かせ、芝生もだいぶ茂ってきました。再来週のサッカー教室が始まる頃にはちょうど良い芝生になっていることでしょう。


暖かくなってきたこともあり、虫たちも活発に動き出しました。先日はテントウムシが一度に4匹も見つかり、発見した園児たちは大興奮していました。

園庭ではその他にもダンゴムシ、ワラジムシ、アリ、アブラムシ、チョウチョウ、ケムシ、ゲジゲジ、キリギリス、クモ、トンボ、ミツバチ、ミミズなどを見つけることができます。過去にはジンガサハムシという変わった虫も発見しました。
 ←ジンガサハムシ
←ジンガサハムシ
小さな園庭ですが、その中にこれだけの虫が隠れていることに驚かされます。そして園児たちは虫を見つけるのがとても上手です。苦手な子もいるとは思いますが、虫を捕まえて眺めているのは「不思議を観察する」という学びでもあります。昆虫は見れば見るほど不思議です。それぞれ特徴も能力も違いますが、自然の生態系を維持していくためにはいずれも不可欠な存在です。

例えばミミズは土を耕し土壌を良くしてくれます。チョウチョウやハチは花から蜜を集める過程で授粉を助けてくれます。テントウムシは植物を枯らしてしまうアブラムシを捕食してくれます。アブラムシはアリに甘露を渡しテントウムシから守ってもらいます。アリは土壌の通気と水はけを良くし、植物が育ちやすい土壌にしてくれます。また腐敗物の分解を助けてくれます。人間の生活にとって益となるか害となるかで、益虫や害虫と分けられていますが、生態系を維持するためにはいずれも必要な存在だといわれています。
私たち人間は、特徴や能力だけでなく性格や感じ方も違います。自分とは違う人たちが集まって、その中で生きていくことを学べる小さな社会が幼稚園です。遠くから観察するだけにとどまらず、関わりを持つことで相手を知り、より良い協力関係が築いていけるよう願っています。