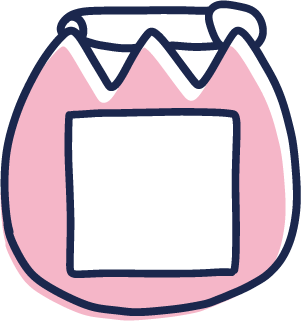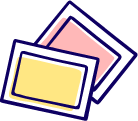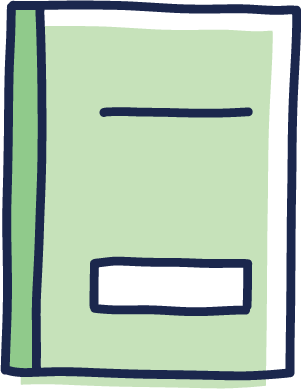
園長便り2025-11
2025.10.03
「育ちに寄り添う保育」
園長:中村貫太郎
先週は札幌市幼稚園連合会教育研究大会の公開保育のため、時間の変更や送迎などにご協力いただきありがとうございました。おかげさまで良き学びの機会をもつことができました。
今回の公開保育では「一人ひとりの育ちに寄り添う保育」をテーマに、学びを深めることができました。子どもの育ちは遊びと深く結びついています。遊びを通して他者との関わり方を学び、成長をしていく場が幼稚園です。しかし、自分で遊びを見つけて楽しめる子もいれば、なかなか遊びに入っていけない子もいます。それは、子ども一人ひとりの発達段階の違いによるものです。

アメリカの発達心理学者のミルドレッド・パーテンは、子どもの遊び方が年齢とともに変化していくことに注目し、その変化が社会性の発達と密接に関連していることを発見しました。そして、子どもの遊びを社会性の発達段階に基づいて次の6つに分類しました。
①無活動(0~3ヵ月頃):目的はなく、座っていたり、周りを眺めている。
(周囲を観察し、刺激を受けることで遊びの土台を築く)
②一人遊び(0~2歳頃):周囲に関心を示さず自分の世界で遊ぶ。
(自分の興味関心に集中し、想像力や集中力が育つ)
③傍観遊び(2歳頃):他の子どもの遊びを観察する。
(他者を観察することで、ルールや関わり方を学ぶ)
④並行遊び(2歳以上):他の子どもの近くで、同じような遊びをする。
(他者との距離感や存在を学ぶ)
⑤連合遊び(3~4歳頃):同じ遊びに参加し、物の貸し借りなど交流が生まれる。
(社会的スキルが育つ)
⑥共同遊び(4歳以上):共通の目的やルールを持ち、役割分担しながら協力して遊ぶ。
(計画を立てる、協力する、問題を解決するなどの力が育つ)
パーテンによるこの分類は、子どもが今どのような発達段階にいるのかを見極める一つの目安になります。ただし、発達のスピードには個人差があります。「3歳なんだから、おもちゃは貸してあげなさい」と年齢だけを根拠に行動を強制するのではなく、遊びの様子からその子どもが今どの段階にいるのかを理解してサポートしていくことが、育ちに寄り添う保育につながっていくのではないかと思います。